こんにちは、Rio(@Rio_reach)です。
生後3ヶ月ごろから、夜はぐっすりと眠っていてくれた息子ですが、
7ヶ月後半ごろから、夜泣きが始まりました。
夜中に起きてしまう日が1回、2回と増えていき、気がついたら毎日0時と3時、6時と3時間ごとに起きるようになってしまいました。
しかも、この夜泣き、原因が全くわからない。

どうしたらいいのかわからず、眠くて、寝不足で、イライライライラ…。
生後7〜9ヶ月は、おすわりやつかまり立ちができるようになったりと、できることが増える時期。
その結果、赤ちゃんの脳みその処理が追いつかず、パニックになってしまうことが夜泣きの原因とも言われています。
今回は、そんな生後7・8・9ヶ月からの夜泣きを脱却するための夜泣きの対策をできるだけたくさん集めてみました!

パッと読むための目次
夜泣きはいつまで?
生後8〜9ヶ月が夜泣きのピークと言われています。しかし、夜泣きには個人差があり、10ヶ月までかかる子もいれば、1歳半までかかる子もいるそうです。

まずはチェックしたい!夜泣きの原因。
昼間、赤ちゃんの脳への刺激が強い

赤ちゃんがたくさんの言葉を吸収するように、たくさん話しかけているママや、胎教や早期教育のために色々な働きかけをしているママもいると思いますが、実は、やりすぎもよくないのです。
よかれと思っておこなった赤ちゃんの脳への刺激が、夜泣きに繋がっていることもあるのです。
引用:こそだてラボ

上記の記事では、以下が赤ちゃんの脳を疲れさせる原因であると書いてあります。該当している項目がないか、一度チェックしてみましょう。
- ママの話しかけ過ぎ
- 昼間にたくさんの人に会った
- 音楽をずっと聞かせている
気温が不快

暑い、寒い、暑いけど寒いなど。
生後10ヶ月未満の赤ちゃんはまだ体温調節がうまくできないので、親が赤ちゃんのいる部屋の温度に気を配ってあげる必要があります。
布団は不快なので、蹴飛ばしてしまうけれども、蹴飛ばした結果寒くなってしまい、夜泣きにつながることも。
夏の室温:26〜28度
冬の室温:20〜23度
湿度は40〜60%を保つようにしましょう。
タイマー設定によりエアコンが切れている

大人だけで生活していたときの名残で、電気代を節約するため、真夜中にエアコンを切っている場合はありませんか?
大人にとっては眠れる温度でも、赤ちゃんにとっては、暑くて寝てられない環境なのかもしれません。
赤ちゃんのために、1日中エアコンはつけておいてあげたり、1時間ごとにON/OFFする設定にしたりしましょう。
実はエアコンの風が直接当たっている
赤ちゃんのベッドに風が直接当たってしまい、赤ちゃんを起こす刺激になっていませんか?
1回確認してみましょう。
オムツが濡れていて不快

と油断していると、オムツがオシッコでずっしり重くなっています。
特に、夜に授乳してしまった時はオシッコの量が増えるので、朝、吸収しきれなかったオシッコにより肌着やズボンが濡れてしまうことも。
歯が生えるムズムズ(歯ぐずり)

歯ぐずりとは、歯が生え始める時期に赤ちゃんが痒みや痛みを感じて、ぐずったり泣いたりすることです。赤ちゃんにより歯ぐずりの程度には差があり、歯ぐずりが殆どない赤ちゃんもいれば、ママが疲れいってしまうほど機嫌が悪くなる赤ちゃんもいます。
参考:歯ぐずりはいつからいつまで?授乳しても寝ないで泣く子への対策
お腹が空いた。母乳が欲しい。
月齢が進んでいるときの夜泣きはお腹が空いたことに起因しないことが多いようですが、それでもお腹が空いたことが原因で泣くことがあります。
母乳ではなくてミルクが欲しい。
息子は母乳とミルク、両方で育っています。
そのせいか、

もしくは、

と言っていることがあります(喋るわけではないので、推測です)。
体調が悪い

風邪をひく前日に夜泣きがひどくなる、といった体験談をよく見かけます。あとは鼻が詰まっているとか、耳に湿疹ができているとか…。
風邪をひいたり、熱があるときも寝付いてくれません。
なんか今日はぐずって寝てくれないなぁ。なんてときは、赤ちゃんの体がいつもより熱くないかチェック!
ちょっとでも熱いと思ったら、体温計を使ってみましょう。
夜泣きの対策1:日常生活の習慣

日々の生活でできる対策を集めました。
生活リズムを整える
生活リズムが整っていないと、活動するべき昼なのか、休息する夜なのか、脳が混乱している状態になると、夜落ち着いて眠れません。
昼に散歩して陽の光を浴びさせ、夜は寝る時間を決めて、寝そうになくても照明を落とした部屋に連れて行き、生活リズムを整えましょう。
同じ儀式で入眠させる
夜、毎回違う儀式で寝かしつけをしようとすると、赤ちゃんがもう寝るべきなのか、そうではないのか不安になってしまうそうです。
同じ時間、同じ寝かしつけ方法(絵本を読む、スキンシップをする、歯磨きするなど)をするようにしましょう。
また、寝かしつけの方法を変える場合は、数日はなかなか寝ないことを覚悟しつつ、
「今日から寝かしつけの方法を変えるよ〜」
と言って、少なくとも3日は続けるようにしましょう。
ねんねのお友達を作る
いつも一緒に寝るぬいぐるみなどをベッドに置いておくと、安心して赤ちゃんが寝てくれるそうです。
(我が家は効果なしでしたが…。)
ぬいぐるみ以外でも、お気に入りの毛布や肌触りのより小物(赤ちゃんの安全性に配慮したもの)でも良いそうです。
寝る前に30分のリラックスタイムを取る

昼間赤ちゃんの脳への刺激が強いと思われる場合は、寝る前の30分間、リラックスタイムを取りましょう。
私がおすすめしている方法は、赤ちゃんをリラックスさせるように夜眠る前に静かな時間をとるということです。
「さぁ、寝よう」という時間の30分前くらいになったら、寝室を暗く、静かにして赤ちゃんにゆっくりと会話する時間をとるようにします。
「今日はたくさんの人に会って疲れたね」「もうゆっくり休んでいいからね」
などと話しかけて、赤ちゃんがリラックスできるように促します。
引用:こそだてラボ
サプリメントを飲ませてみる

写真引用:薬事日報
実は、夜泣きの原因は赤ちゃんのおなか痛、「乳児疝痛」(にゅうじせんつう)の可能性があります。
原因はよくわかっていないらしいですが、赤ちゃんのお腹の中の菌の環境が出来上がる過程で発生すると言われています。

この「乳児疝痛」に効果があるサプリメントが「チャイルドヘルス」。
赤ちゃんにサプリメントをあげるなんて、少し抵抗があるかと思いますが、「チャイルドヘルス」はサプリメントというよりも、乳酸菌なので、ヨーグルトを食べている感覚に近いです。
与える量は、1日5滴。
母乳由来のロイテリ菌(乳酸菌)を与えることで、赤ちゃんがないている時間を4分の1になったというデータがあります。
新生児から使え、安全性も徹底しており、世界最高峰の安全認証「GRAS」の認証を受けているとのこと。
危険なものではないので、試してみるといいかもしれません。
また、チャイルドヘルスを販売しているバイオガイアの「夜泣き度セルフチェック」がとても参考になります。もちろん、無料で診断できるので、夜泣きに悩んでいる方はぜひやってみて下さい。
生薬(漢方)を飲ませてみる
生薬(漢方)を試してみるのもよいでしょう。
代表的なのはこの2つ。
- 樋屋奇応丸(ひや・きおうがん)
- 宇津救命丸(うずきゅうめいがん)
どちらの薬も、名前だけはどこかで聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
樋屋奇応丸(ひや・きおうがん) は、生後2週間経過し、体重が順調に増えていれば服用可能です。
ただし、生後2週間で飲ませるのは不安がありますよね?
念のため薬剤師さんに相談するのがいいと思います。
宇津救命丸(うずきゅうめいがん)は生後3ヶ月から服用可能です。
どちらのお薬も小さい球になっているので、飲ませるのにはさほど苦労しません。
離乳食やミルクに混ぜてあげたりしましょう。
夜泣きの対策2:部屋の環境

寝る環境や、衣類での気温調整などの対策を集めました。
遮光カーテンを使ってみる
夏、早朝に起きてしまう光に敏感な赤ちゃんには、遮光カーテンをつけてあげて、まだ起きる時間でないことを教えてあげましょう。

子供用はらまきを使ってみる
夏、布団を蹴飛ばしてしまったり、布団を嫌がる赤ちゃんにオススメなのが、子供用のはらまき。
夏用のスリーパーも考えましたが、冷房も26度に設定しているし、その中で布団をかけずに寝ている状態で汗をかいているので、スリーパーはより暑くなってしまうと判断しました。
布団をかけない代わりに、はらまき。

スリーパーを使ってみる
冬、布団を蹴飛ばしてしまう赤ちゃんはスリーパーを使ってみましょう。
アロマを使ってみる
有名なのが、「ベビースリープ」というアロマオイル。
原料は、ベルガモット(果皮)・ラベンダー(花穂)・クラリセージ(花・葉)。
ベルガモット、ラベンダーはリラックス効果、クラリセージには女性のホルモンバランスを整えたり、ストレスを緩和する効果があると言われています。
香りで「これから寝る時間だよ」と赤ちゃんに伝える入眠儀式にしていきましょう。 夜、寝る前のディフューザーを使った芳香浴はもちろん、赤ちゃんとの添い寝時にママのパジャマや枕に一滴垂らして使用するのもおすすめです。
引用:AMOMA
香りを入眠の刺激にするのはいいアイディアだと思います。
我が家は「ねんねのお友達」を作るのに失敗したので、このアロマを入眠儀式に取り入れていきたいと思います。
取り入れたらブログで報告します!!
ネット上では、乳児だけでなく、幼児にも効果あり!との報告もありますので、ぜひ一度試してみて下さい!
夜泣きの対策3:起きてしまい、再び眠りにつかせたい時

我が家で一番悩んでいるのがこれです。決まった時間に入眠はできるけれども、再度眠りにつくことが難しい。
背中やお尻をトントンする
保育士さんがよく使っているのを見かけます。一定のリズムで、トントンしてあげると、赤ちゃんが安心し、眠りに誘われるようです。
我が家でも何回かはトントンでなんとかなることもあります。
オムツを交換する

夏はオムツが蒸れるのか、オムツを交換している途中で再度寝てくれることがあります。
そんなときは、暑かったのかなぁ、と思いつつ、ズボンをせめてはかせずに眠らせています。
おしゃぶりをくわえさせる
何かをしゃぶりたい、という欲求に答えてくれるのがおしゃぶりです。
授乳前に一度試してみるといいですね。
また、おしゃぶりは月齢別になっているので、忘れずに買い替えたいですね。

歯固めになるようなおもちゃをくわえさせる
歯ぐずりの場合、歯がため用のおもちゃや、お気に入りの噛むものをくわえさせると、くわえたまま寝てくれることもあります。
パパが抱っこしてみる

あまり効果がない気もしますが(笑)、ママが抱っこしてばかりだと疲れるので、パパに抱っこしてもらうこともあります。

もしくは、最後だけパパに抱っこしてもらうとか。
万が一泣いてしまっても、すぐにママに返してもらえばOKです。
ママが抱っこしてみる
なるべくなら避けたいですが、どうしようもないときはママが抱っこです。
生後7ヶ月以上になると重いですよね。たまにはマッサージにでも行って自分を癒しましょう。
ママは、自分を労わることになぜか無頓着になりがちなのです。
別の部屋に寝かせてみる

寝る環境をガラッと変えてみると、なぜか寝るときがあります。気分転換になるのでしょうか。
大人と一緒ですね。
抱っこしてゆらゆらする
抱っこゆらゆらは新生児からの定番。抱っこしてひたすら歩きます。

母乳をあげてみる(添い乳)

抱っこゆらゆらで寝そうもない場合は仕方ないので、母乳をあげてみます。

続くようなら、寝る前の授乳量を増やしたり、夜中12時ごろに一回起こして授乳する、と言ったことが必要になるかもしれません。
添い乳で寝てくれると、背中スイッチが発動するリスクがないのでラクです。
母乳をあげてみる(起きた状態)
背中スイッチが発動する危険性はあるものの、ぎゃん泣きしている場合、経験から起きた状態で母乳をあげたほうが入眠する可能性が高いように感じています。
ミルクをあげてみる

母乳で足りないのか、母乳を吸う元気がないのか、ミルクがやっぱりいい時があるみたいです。
ミネラルアクアをあげてみる
※2018年6月22日 追記
ミネラルアクアは、ピジョンから発売されている電解質飲料。ようは、ポカリスウェットを薄くしたような飲料です。
失った水分を素早く補給できます。
3ヶ月から飲めます。
我が家は、すっごくぎゃん泣きしているときは、ミルクよりも母乳よりも、ミネラルアクアを飲ませる方が効果あり!でした。
こっちの方がおいしいのかな?
完全に起こして遊ぶ
ママは辛いですが、完全に起こすと、泣きやむことが多いです。
赤ちゃんが目を閉じながら泣いている時って、半分寝ていて、半分起きているという、赤ちゃんにとって不快な状態です。

完全に起こすことにより、赤ちゃんにとっての不快な状況を脱出させて、まずは泣き止ませることができます。
起きた状態で、2時間くらいすると、

と言って、ちょっとぐずった状態になります。
その機をきちんと見計らって、抱っこゆらゆらすると寝てくれます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
可愛い我が子でも、正直毎日夜泣きされると、余裕もなくなってしまいますよね。
頑張るしかないと思っていても、頑張れなくなってしまいます。
夜泣きを改善するためにも、一つ一つ、夜泣きの要因を無くすことを心がけて、改善を目指していきたいですね。
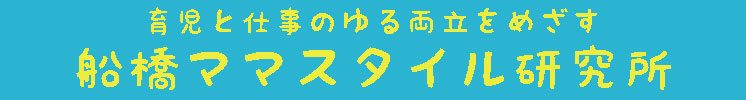








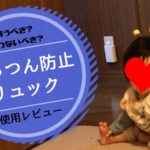






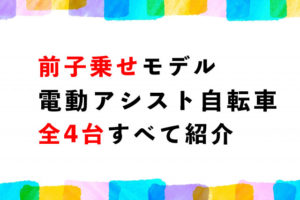

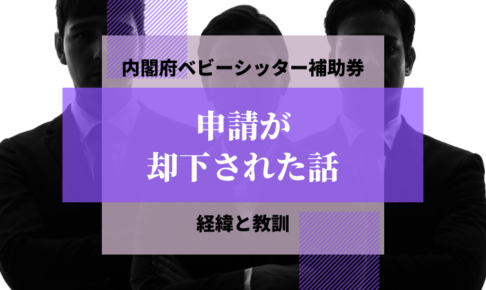



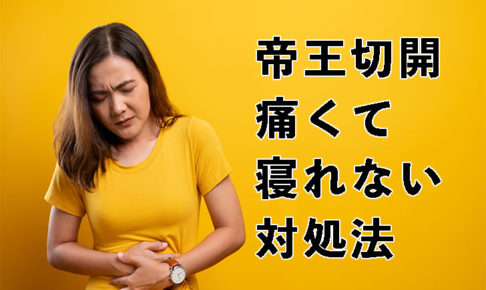


子守歌を歌ってみてもダメ。
抱っこしてみても、身体を反らせまくる。
かと言って、布団に置いても効果なし。